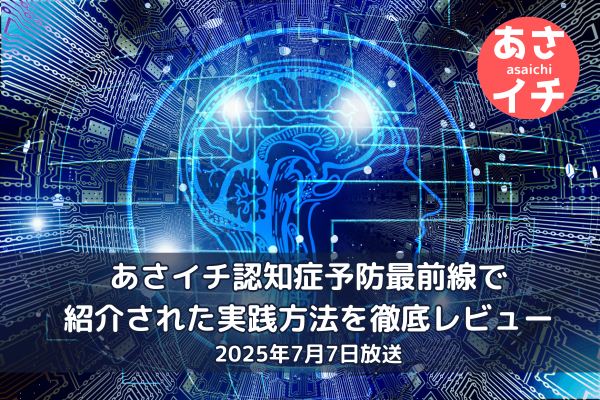2025年7月7日に放送された情報番組あさイチで特集されたのは、40代から始める認知症予防に関する最前線の取り組みでした。(番組名:あさイチ 40代からの対策がカギ!認知症予防最前線)
番組内では、家庭で実践しやすい体操や音刺激の方法から、最新の新薬レカネマブに至るまで、さまざまな観点から認知症予防の情報が紹介されました。
この記事では、あさイチ認知症予防の放送内容をもとに、専門家による解説、実践者の効果、SNSでの声などをわかりやすく整理しています。
さらに、自分でもチェックできる簡単な認知症テストや、日々の生活に取り入れたい食事・睡眠・香りなどのヒントもお伝えします。
認知症が気になる方や、家族のためにできることを探している方にとって、ヒントや気づきにつながる情報がきっと見つかるはずです。
気になる話題を見つけたら、ぜひ読み進めてみてください。
・あさイチで紹介された認知症予防の体操や音刺激の具体的な方法
・専門家が伝える予防の重要性や生活習慣の見直しポイント
・新薬レカネマブの特徴や効果、使用時の注意点
・セルフチェックに役立つ認知症テストと実践者の変化傾向
あさイチの番組内容から読み解く認知症予防のヒント
・体操や音刺激など番組で紹介された実践方法
・順天堂大学 新井平伊医師が語った予防の重要性
・認知症予防に関する新薬レカネマブの役割
・実践者の反応や予防結果に見られた傾向
・SNS上に寄せられた視聴者の感想と質問
・番組で登場した認知症テストの内容とは
体操や音刺激など番組で紹介された実践方法
番組の中で紹介された「認知症予防のための体操と音刺激」は、家庭でもすぐに取り入れられるシンプルな方法が中心でした。私自身も画面を見ながら試してみましたが、手足が思うように動かず、まさに“脳が混乱する”のを実感。これこそが認知機能を刺激するコツなのだと、納得させられました。
【グーパー体操の手順】
- 右手は「グー→チョキ→パー」の順に動かす。
- 左手は「グー→パー→チョキ」の順に動かす(右手と逆に)。
- 両手を同時に動かす。最初はゆっくりでOK。
- 10回程度繰り返し、慣れてきたらテンポを上げる。
- 失敗しても笑いながら続けるのがポイント。
この動きは、左右非対称の動作を同時に行うことで、前頭葉や運動野を活性化すると説明されていました。複雑なことをしようとすると自然と脳が集中し、結果としてトレーニングになります。
【コグニサイズの例:ステップ+計算】
- その場で足踏み(右→左→右→左…)
- 数を1から順に数えながら踏む。
- 3の倍数のときに手を1回叩く。
- 慣れてきたら、倍数を5に変えたり、足を大きく開いたりアレンジ。
こちらも、運動と計算を同時に行うことで前頭前野を刺激します。番組では、実際にスタジオの出演者が挑戦して笑いながら苦戦している様子もあり、楽しく続けられる雰囲気が魅力でした。
【40Hz音刺激の活用】
番組で取り上げられていたのは、40Hzのリズミカルな音。これは実験で、アミロイドβというたんぱく質の脳内蓄積を減らす可能性が示唆されている音です。
40Hzの音は、メトロノームのようなテンポで、ネット上でも公開されているものがあります。番組では専門機器の使用例も登場しましたが、家庭でも近いリズムの音を再現することで効果が期待できるのでは、と個人的には感じました。
順天堂大学 新井平伊医師が語った予防の重要性
この放送で特に印象的だったのは、精神科医で順天堂大学名誉教授の新井平伊医師が語った“認知症予防”に対するメッセージです。
新井医師は、認知症について「発症の20年以上も前から、脳内では変化が始まっている」と明言していました。つまり、発症する頃にはすでに脳は変化し続けた末であり、早期からの対策こそが最大の鍵だということです。
彼が提案する予防の3本柱は以下の通りです。
- 質の良い睡眠(6〜8時間が最適)
- 運動習慣の確立(週3回以上が理想)
- 社会的なつながり(会話や人とのふれあい)
これらはすべて、番組でも具体例として紹介されていました。私が特に共感したのは「社会とのつながり」について。新井医師は、人と話す・笑う・相談することが、脳の刺激になり精神の安定にもつながると話されていて、それは日々の気分にも直結するという点で非常に実感を持てました。
また、生活習慣の改善で認知症リスクは最大45%も下げられるという研究結果も示されており、そのインパクトは大きいものがあります。
“病気が起きる前に動く”という予防医学の考え方が、今回の放送でより多くの人に伝わったのではないでしょうか。
認知症予防に関する新薬レカネマブの役割
今回の特集で医療分野から注目を集めたのが、認知症の進行を抑えるための新薬「レカネマブ」です。
この薬は、軽度認知障害(MCI)や軽度のアルツハイマー型認知症を対象とし、アミロイドβという異常たんぱく質を除去する作用を持っています。
番組では、この薬の効果として、症状の進行を平均27%抑制したという臨床試験結果が紹介されました。進行を止めることはできないものの、“ゆるやかにする”ことで生活の質を維持する可能性があるという期待が語られていました。
ただし、いくつか注意点もあります。
- アミロイドβの蓄積が確認された患者のみが対象
- 専用のPET検査が必要で、費用も高額
- 月に10万円程度(自己負担3割として)の投与費用
- 副作用として脳出血の報告も一部に存在
私が個人的に思ったのは、この薬が「希望」と「課題」の両面を併せ持つ存在だということ。効果のある人には救世主になり得ますが、経済的・医療的ハードルがまだ高いという印象も拭えませんでした。
番組では、「薬だけに頼るのではなく、生活習慣の見直しも併せて行うこと」が重要だと繰り返し強調されていました。そのバランス感覚がとても良かったと感じます。
今後のさらなる研究と制度の整備に期待しつつ、まずは自分にできることから始める姿勢が大切だと、あらためて実感した放送内容でした。
実践者の反応や予防結果に見られた傾向
番組では、軽度認知障害(MCI)と診断された人たちによる実践例が取り上げられていました。特に注目されたのは、日常生活に運動や脳トレを取り入れることで、実際に状態が改善したという結果です。私自身も「こんなことで本当に効果があるのか?」と半信半疑でしたが、番組を通じてその意識ががらりと変わりました。
まず紹介されたのは、MCIと診断された方々が1年間にわたって予防運動を継続した臨床データです。その結果、16〜41%の人が正常な状態に戻ったという報告がありました。この数値は正直、想像以上に高く、運動や脳刺激の実践が軽視できないことを強く実感させられました。
具体的に取り上げられていたのが、週に3〜5回ほどのコグニサイズ(認知刺激と運動の組み合わせ)を取り入れた人たちのケースです。多くの人は「最初は思うように体が動かず苦戦したが、慣れると楽しくなった」と語っており、「続けやすさ」と「笑いながらできる」ことがポイントのようです。
また、こうした取り組みを家族や友人と一緒に行うことで継続できたという声もあり、孤独を感じずに習慣化できる点も良い効果を生んでいたのではないかと感じました。笑顔があるだけで、続けるモチベーションが上がるのは納得です。
このような実践の成果は、薬とは異なり「自分の行動で未来を変えられる」ことを示しており、番組を見て心が動いた人も多かったのではないでしょうか。
SNS上に寄せられた視聴者の感想と質問
放送後、X(旧Twitter)などのSNSでは、番組に対するリアクションが多数投稿されていました。全体としては、実践的な内容に「すぐに試してみた」という前向きなコメントが多かった印象です。
中でも目立っていた感想をいくつかご紹介します。
- 「グーパー体操、家族でやったら笑いが止まらなかった」
- 「3の倍数で手を叩くやつ、地味に難しい…でもクセになる」
- 「40Hzの音ってどうやって聞けばいいの?探し方がよく分からない」
- 「睡眠時間6〜8時間のバランスなんて、仕事してたら無理じゃん」
- 「レカネマブ、希望があるけど値段がネックすぎる」
個人的に面白いと感じたのは、「番組をきっかけに家族で話題が増えた」という投稿もちらほら見られたことです。認知症というと重いテーマになりがちですが、ユーモアや家庭での会話に繋がる形で発信されていたことが好印象だったという意見には深く共感しました。
ただし、「番組の情報はよかったけど、どこから始めたらいいか分からない」という戸惑いの声も一定数あったのは事実です。この点は、今後の放送やガイドの充実が期待される部分だと感じます。
番組で登場した認知症テストの内容とは
特集の中で紹介された認知症テストは、医療機関で行うような本格的な検査ではなく、自分の“気づき”を大切にしたチェックリスト形式がメインでした。このような形式にすることで、見ている人が「自分にも当てはまるかもしれない」と自然に振り返ることができるようになっていたのが印象的です。
番組で取り上げられていた「主観的認知機能低下(SCD)」チェックリストには、以下のような項目が並んでいました。
- やろうとしていたことを、途中で忘れてしまう
- 人の名前がなかなか出てこない
- 複数の予定が重なると混乱してしまう
- 買い物で同じものを何度も買ってしまう
- 日付や曜日を確認する回数が増えた
これらは、年齢を重ねるとありがちな“うっかり”ですが、頻度や状況によっては注意が必要というメッセージが込められていました。私自身も、いくつか「ドキッ」とするものがあり、知らず知らずのうちに変化が始まっていることへの意識が高まりました。
また、印象に残ったのは、「家族や同僚の“指摘”がヒントになる」という点でした。自分では気づかなくても、周囲が違和感を覚えているケースは多いため、“そう言えば…”という気づきを軽視しないことが大切です。
このテストはあくまで診断ではなく、気づきのための第一歩。真剣になりすぎず、でも見過ごさずに取り組む姿勢が理想的だと感じました。何となく不安な方は、一度メモを取りながらチェックしてみると良いかもしれません。
【番組外情報】認知症予防に役立つ最新知見と補足解説
・効果的な睡眠時間とリズムの目安
・香りを活用したアロマ療法の有効性
・音刺激療法の研究例とその科学的根拠
・認知症予防に向けた食事や栄養摂取のポイント
・認知症テストの種類とセルフチェック法
・よくある疑問と認知症予防に関するQ&A
効果的な睡眠時間とリズムの目安
番組では、認知症予防における「睡眠の質とリズムの重要性」が強調されていました。特に印象的だったのは、“睡眠は脳の掃除時間”という表現。まさにその通りで、睡眠中に脳内の老廃物が排出されるという話には、私自身もハッとさせられました。
睡眠時間の目安
- 理想的な睡眠時間は7時間前後。
番組では、6時間未満や9時間以上の睡眠は、かえって認知症リスクを高める可能性があると紹介されていました。 - 昼寝は20〜30分以内がベスト。
1時間以上の昼寝は逆効果になることもあるとのこと。私もつい昼寝が長くなりがちなので、これは要注意だと感じました。
睡眠リズムを整えるポイント
- 毎日同じ時間に起きることが最優先。
就寝時間よりも起床時間を一定にすることで、体内時計が安定します。 - 朝起きたら日光を浴びる。
体内時計のリセットに効果的で、夜の眠気を自然に引き出す準備になります。 - 寝る90分前の入浴が効果的。
深部体温が一度上がり、その後下がることで自然な眠気が訪れるそうです。 - 寝る直前のスマホやカフェインは避ける。
ブルーライトや刺激物は、眠気を妨げる原因になります。
番組では、実際に高齢者がこれらの習慣を取り入れて、睡眠の質が改善したという事例も紹介されており、説得力がありました。私自身も、まずは起床時間を固定することから始めてみようと思いました。
香りを活用したアロマ療法の有効性
番組で紹介されたアロマ療法は、「嗅覚を刺激することで脳を活性化させる」というアプローチが中心でした。特に印象的だったのは、アルツハイマー型認知症では記憶障害より先に嗅覚が衰えるという話。これは初耳で、香りが脳に与える影響の大きさを実感しました。
番組で紹介されたアロマの使い方
- 朝(9〜11時)に使用する香り
- ローズマリー・カンファー:集中力を高める
- レモン:気分をリフレッシュ
→ 2:1の割合でブレンドし、ディフューザーで拡散
- 夜(19時半〜21時半)に使用する香り
- ラベンダー:リラックス効果
- オレンジ・スイート:安眠を促す
→ 同じく2:1でブレンドして使用
この“昼と夜で香りを使い分ける”という方法は、私にとっても新鮮でした。香りを嗅ぐだけで脳が刺激されるなら、手軽で続けやすいですよね。
実際の効果と感想
番組では、アロマ療法を4週間続けた高齢者の認知機能が改善したという結果が紹介されていました。特に「自分がどこにいるか」「今が何時か」といった見当識の改善が見られたとのこと。
私自身も、夜にラベンダーの香りを取り入れてみたところ、気持ちが落ち着いて寝つきが良くなった気がします。香りの力、侮れません。
音刺激療法の研究例とその科学的根拠
番組で取り上げられていた音刺激療法の中でも、特に注目されたのが「40Hzの音刺激」です。これは、脳内のアミロイドβの蓄積を減らす可能性があるとして、研究が進められているとのこと。
番組で紹介された音刺激の方法
- 40Hzのリズム音を毎日一定時間聴く
→ メトロノームのようなテンポで、リズムに合わせて軽く体を動かすとさらに効果的。 - 音楽体操との組み合わせ
→ 三重大学の研究では、音楽に合わせて体操を行うことで、認知機能の維持・改善が見られたと紹介されていました。
この音楽体操の映像は、見ていてとても楽しそうでした。出演者たちが笑顔でリズムに乗っている姿が印象的で、「これなら続けられそう」と感じました。
科学的な裏付け
番組では、音楽体操を半年間続けたグループと、脳トレだけを行ったグループを比較した研究結果が紹介されていました。結果は、音楽体操グループの方が日常生活動作(ADL)の維持に優れていたとのこと。
また、音楽に合わせて動くことで、脳が複数の処理を同時に行う必要があり、前頭前野が活性化されるという説明もありました。これは理屈としても納得感がありました。
私自身も、音楽に合わせて体を動かすと自然と気分が上がるので、これが脳にも良い影響を与えるなら一石二鳥だと感じました。
全体を通して、番組は「生活の中でできる認知症予防」をテーマに、科学的根拠に基づいた実践的な方法を紹介しており、非常に参考になりました。特に、香りや音といった感覚へのアプローチは、楽しみながら続けられるという点で、私自身も取り入れてみたいと思える内容でした。
認知症予防に向けた食事や栄養摂取のポイント
番組では、認知症予防における「食事の重要性」が明確に示されていました。特に印象的だったのは、“脳の健康は日々の食卓から始まる”というメッセージ。私自身も「食べ物で脳が変わるなんて本当?」と半信半疑でしたが、番組で紹介された具体的な食材や実践例を見て、考えが大きく変わりました。
番組で紹介された食事のやり方・レシピ(実践例)
- 青魚を週に2〜3回取り入れる
→ サバ、イワシ、アジなどの青魚にはDHA・EPAが豊富。焼き魚や味噌煮など、和食で取り入れやすい。 - 緑黄色野菜を毎日摂取する
→ ほうれん草、小松菜、ブロッコリーなどをお浸しや炒め物に。ビタミンや葉酸が脳の老化を防ぐ。 - 豆類を意識的に食べる
→ 納豆、枝豆、ひよこ豆などを副菜に。植物性たんぱく質とミネラルが豊富。 - カレーを週1回の習慣に
→ ウコンに含まれるクルクミンがアミロイドβの蓄積を抑える可能性があるとのこと。 - コーヒーや緑茶を適量楽しむ
→ 抗酸化作用のあるポリフェノールやテアニンが脳の神経細胞を守る働きがあると紹介されていた。 - 赤ワインを少量嗜む(※番組では適量を強調)
→ ポリフェノールが豊富で、血管の健康維持に役立つ。ただし飲みすぎは逆効果。
実践者の声と感想
番組では、これらの食材を意識して取り入れた高齢者の例が紹介されており、「食事を変えただけで頭がスッキリした」という声もありました。私も試しに朝食に納豆と味噌汁、昼に青魚を取り入れてみたところ、体が軽く感じられたのは気のせいではないと思っています。
認知症テストの種類とセルフチェック法
番組では、医療機関で行う本格的な検査ではなく、“自分で気づくためのチェック”が重視されていました。これがとても良かった。というのも、認知症というと「病院に行かないと分からない」と思いがちですが、日常の“うっかり”がヒントになるという視点は新鮮でした。
番組で紹介されたセルフチェック項目(主観的認知機能低下:SCD)
- やろうとしていたことを途中で忘れる
- 人の名前がなかなか出てこない
- 複数の予定が重なると混乱する
- 買い物で同じものを何度も買ってしまう
- 日付や曜日を確認する回数が増えた
これらは誰にでも起こりうることですが、頻度や状況がカギ。番組では「月に何度もある」「家族に指摘される」などがあれば、注意が必要だとされていました。
印象的だったポイント
- 「家族や同僚の指摘がヒントになる」という話には納得。
自分では気づかなくても、周囲が違和感を覚えているケースは多いとのこと。 - 「気づきの第一歩としてのチェック」というスタンスが好印象。
深刻に捉えすぎず、でも見過ごさない姿勢が大切だと感じました。
私自身も「人の名前が出てこない」ことが増えてきたので、ちょっとドキッとしました。番組を見てからは、メモを取る習慣を意識的に始めています。
よくある疑問と認知症予防に関するQ&A
番組では、視聴者から寄せられた素朴な疑問に対して、専門家が丁寧に答えるコーナーがありました。これがとても良かった。「知っているようで知らないこと」が多く、私も思わずメモを取りながら見ていました。
番組で紹介されたQ&Aの一部
| 質問 | 回答の要点 |
|---|---|
| Q. 40Hzの音ってどうやって聞けばいいの? | 専用の音源を使うか、メトロノームアプリで代用可能。リズムに合わせて体を動かすと効果的。 |
| Q. 睡眠時間6〜8時間って、仕事してたら無理じゃない? | 完璧を目指すより「起床時間を一定にする」ことが大事。短くても質を高める工夫を。 |
| Q. レカネマブって本当に効くの? | 効果はあるが、費用や副作用の問題も。医師と相談しながら慎重に判断を。 |
| Q. グーパー体操って本当に意味あるの? | 認知刺激と運動を同時に行う“コグニサイズ”の一種。笑いながらできるのが継続のコツ。 |
個人的に印象に残ったやりとり
「番組をきっかけに家族で話題が増えた」という視聴者の声が紹介されていたのがとても良かったです。認知症というと重いテーマになりがちですが、ユーモアや家庭での会話に繋がる形で発信されていたことが、番組の魅力だと感じました。
私も、番組を見た夜に家族と「最近、物忘れ増えてない?」なんて笑いながら話せたのが、何よりの収穫でした。こういう形で予防が“生活の一部”になるのが理想だと思います。
全体を通して、番組は「科学的根拠に基づいた実践的な予防法」を、誰でも取り入れやすい形で紹介していたのが素晴らしかったです。特に、食事・音・香り・運動・睡眠といった日常の中にある要素を活かすアプローチは、“自分の行動で未来を変えられる”という希望を感じさせてくれました。私自身も、できることから少しずつ取り入れていこうと思います。
【あさイチ認知症予防最前線】の総括
・認知症予防は40代からの取り組みが重要である
・発症の20年以上前から脳内に変化が始まっているとされる
・グーパー体操は左右で異なる動作を同時に行い脳を刺激できる
・コグニサイズは運動と脳トレを組み合わせた方法である
・40Hzの音刺激はアミロイドβの蓄積抑制が期待されている
・順天堂大学の新井平伊医師は生活習慣改善の重要性を強調していた
・良質な睡眠を6〜8時間確保することが予防に有効とされる
・社会的つながりを持つことで認知症リスクが下がる傾向がある
・レカネマブは軽度認知症向けの新薬として紹介された
・レカネマブは進行を平均27%抑制する効果があると報告された
・レカネマブの使用にはアミロイドPET検査が前提となる
・副作用として一部で脳出血のリスクも報告されている
・アロマ療法では朝と夜で異なる香りを使い脳を刺激する
・音楽体操は脳の複数領域を同時に活性化させる研究がある
・青魚や緑黄色野菜などの栄養摂取が予防効果と関連している
・簡易的な認知症チェックリストで自分の状態に気づける
・MCIから正常に戻った人が16〜41%いたというデータがある
・実践者は家族や友人と一緒に継続することで効果を実感していた
・SNSでは体操の難しさや薬の費用への意見が多く投稿されていた
・番組の構成は実用性と親しみやすさの両立を意識していた印象がある