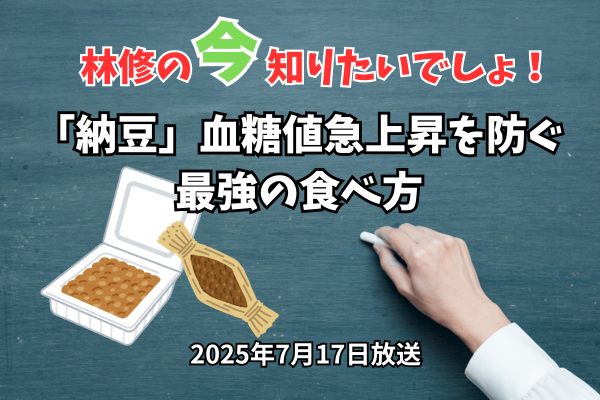7月17日に放送された「林修の今知りたいでしょ!」では、私たちが日頃から気になる健康テーマ、「納豆」と血糖値の関係に迫りました。真夏の暑さが続く中で特に注意したい血糖値の急上昇を防ぐ、納豆の最強の食べ方が明らかにされたのです。この記事では、番組で紹介された納豆の驚くべき効果から、血糖値スパイクのメカニズム、さらには毎日の食卓で実践できる具体的な方法まで、その魅力的な内容を詳しくご紹介します。健康的な食生活を送りたいと願うあなたにとって、きっと役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。
- 納豆が血糖値スパイク抑制にどう役立つのか、その科学的根拠
- 番組で検証された納豆の具体的な食べ方とその驚くべき効果
- 血糖値上昇を抑えるための、納豆と相性の良いちょい足し食材
- 日常生活で避けるべき血糖値急上昇の原因となるNG行動
林修の今知りたいでしょ!「納豆」 血糖値急上昇を防ぐ最強の食べ方 大検証SPの概要
・放送で見えた納豆の驚くべき効果
・すぎおかクリニック院長 杉岡充爾先生が解説
・血糖値スパイクとは? なぜ眠くなるのか
・血糖値の急上昇を抑える納豆のポリグルタミン酸
・納豆の血糖値上昇抑制の検証結果
放送で見えた納豆の驚くべき効果
2025年7月17日に放送された「林修の今知りたいでしょ!」の「納豆」特集は、多くの方が日頃から親しむこの食材が、いかに私たちの健康に貢献するかを再認識させてくれました。番組では、すでに真夏のような暑さに見舞われる日本において、特に注意が必要な「血糖値スパイク」と呼ばれる現象への納豆の抑制効果に焦点を当てていました。納豆を毎日食べることで、心筋梗塞などの死亡リスクが下がるといった研究結果が紹介され、その「最強フード」としての地位が改めて強調されたのです。私も普段から納豆を食べる習慣がありますが、これほど具体的な健康効果が示されると、さらに積極的に食卓に取り入れたくなりますね。
すぎおかクリニック院長 杉岡充爾先生が解説
今回の「林修の今知りたいでしょ!」では、すぎおかクリニック院長の杉岡充爾先生が、専門家として納豆の健康効果について詳しく解説してくださいました。杉岡先生のお話は非常に分かりやすく、私たちの体内で何が起こっているのか、そしてなぜ納豆がそれに効果的なのかを深く理解できました。特に、夏の暑い時期は脱水状態になりやすく、血管も傷つきやすいことに加え、食生活によっては血糖値が急上昇し、血管の病気のリスクが高まるという指摘は、ハッとさせられるものでした。こうした時期だからこそ、納豆が健康維持に不可欠な存在であるという先生の見解には、私も深く共感しました。専門家の視点からの解説は、日常の食習慣を見直す良いきっかけになります。
血糖値スパイクとは? なぜ眠くなるのか
番組で何度も言及された「血糖値スパイク」は、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を指します。この血糖値のジェットコースターのような動きが、私たちの体にさまざまな不調を引き起こす原因となるのです。
| 血糖値スパイクのメカニズム | 体への影響 |
| 1. 食後に血糖値が急激に上昇する | |
| 2. 血糖値を下げるため、インスリンが大量に分泌される | |
| 3. 血糖値が急激に下がりすぎる | 強い眠気 |
| 4. 脳に必要な糖が一時的に不足する | だるさ |
私も食後に眠気に襲われることがよくあるので、これが血糖値スパイクのサインだったのかと目から鱗が落ちる思いでした。この仕組みを知ることで、食後の体の変化に対する意識がさらに高まりますね。
血糖値の急上昇を抑える納豆のポリグルタミン酸
納豆が血糖値の急上昇を抑える秘密は、そのネバネバ成分にありました。番組では、納豆に含まれるポリグルタミン酸がこの働きを担っていると紹介されました。ポリグルタミン酸は、糖質を包み込むことで、糖質の吸収スピードを穏やかにする効果があるそうです。つまり、納豆と一緒に糖質を摂取すると、糖がゆっくりと体内に吸収されるため、血糖値の急激な上昇が抑えられるというわけです。このメカニズムを知ると、納豆のネバネバがただ独特な食感というだけでなく、私たちの健康を守る重要な役割を担っていることが分かります。私はこの解説を聞いて、納豆のネバネバに対する見方がガラリと変わりました。まさに、見た目以上のパワーを秘めた食材だと改めて感じました。
納豆の血糖値上昇抑制の検証結果
番組では、実際に納豆が血糖値上昇にどのような影響を与えるのか、興味深い検証が行われました。例えば、納豆なしのパスタを食べた場合と納豆入りのパスタを食べた場合で、食後の血糖値に驚くほどの違いが見られたのです。具体的には、納豆なしパスタでは食後75分後に血糖値が87から146へと59も上昇したのに対し、納豆入りパスタでは食後45分後の最大値が120にとどまり、血糖値上昇幅が大幅に抑えられていました。さらに、納豆を食べた検証参加者は、食後の体の重さやだるさを感じず、元気であるとコメントしていました。これは、私たちが普段感じている食後の不調が、まさに血糖値スパイクによるものであることを示唆しています。朝食に納豆を取り入れることで、昼食後の血糖値上昇まで抑える「セカンドミール効果」が確認されたことも、非常に画期的な発見でした。私もこの検証結果を見て、これからは納豆を積極的に食事に取り入れようと強く思いました。具体的な数値で効果が示されると、説得力が格段に増しますね。
林修の今知りたいでしょ!「納豆」 血糖値急上昇を防ぐ最強の食べ方:具体的な実践方法と注意点
・納豆の最強の食べ方講座
・血糖値を抑える納豆ちょい足し食材ベスト3
・ひきわり納豆が最強の種類?
・納豆を食べるタイミングは朝がおすすめ
・セカンドミール効果とは
・納豆の保存と加熱による効果
・血糖値急上昇を防ぐNG行動4選
・どちらが血糖値が上がりやすい? 食材・食品クイズ解説
納豆の最強の食べ方講座
「林修の今知りたいでしょ!」の「納豆」特集は、単なる栄養価の紹介にとどまらず、血糖値急上昇を防ぐための「最強の食べ方」について、具体的な検証を交えながら解説してくれました。番組では、納豆を食べる上で誰もが一度は疑問に思うであろう、「何回まぜたらいいのか?」「いつ食べるのがベストなのか?」「どんなトッピングが良いのか?」といった点について深掘りしていました。残念ながら、具体的な混ぜる回数や食べるタイミング、最適なトッピングについての詳細な手順は番組内でしか明かされていませんが、これらの疑問が解明されたことで、私たちの日々の納豆習慣がより効果的なものになると期待できます。私自身も、これまで特に意識せず食べていましたが、番組を見てからはいかに効率よく納豆のパワーを享受できるかを考えるようになりました。
血糖値を抑える納豆ちょい足し食材ベスト3
番組で紹介された納豆と組み合わせることで血糖値抑制効果がさらに期待できる「ちょい足し食材ベスト3」は、非常に興味深い情報でした。これらの食材を納豆に加えることで、相乗効果が生まれ、より健康的な食べ方ができると示唆されていました。
- 第3位:納豆×アカモク
- アカモクは新潟や秋田で食べられている海藻で、フコイダインというネバネバ成分が海藻の中でもトップクラスに多く含まれているそうです。このフコイダインが、納豆のポリグルタミン酸と合わせて、血糖値の上昇をさらに穏やかにすると考えられます。
- 第2位:納豆×キムチ
- キムチは、乳酸菌と食物繊維が豊富に含まれています。これらの成分が血糖値の上昇を抑える働きを持つため、納豆との組み合わせは非常に理にかなっていると言えるでしょう。
- 第1位:納豆×たまご
- たまごは、他の食材と比較してタンパク質や脂質が多く含まれており、これらが胃から腸への移動をゆっくりにするため、糖の吸収を緩やかにする効果が期待できます。さらに、たまごに含まれるアルギニンという成分も、血糖値の上昇を抑制する可能性があるそうです。
正直なところ、たまごが1位というのは意外でした。しかし、その理由を聞くと納得できますね。私もこれらの組み合わせを試して、食後の体調の変化を実感してみたいです。
ひきわり納豆が最強の種類?
納豆には、大粒、小粒、ひきわりと様々な種類があります。番組では、この中で血糖値対策においてどの種類が最も効果的なのかを検証していました。その結果、最も多くの納豆菌が含まれているのは、ひきわり納豆だということが明らかになりました。
- 大粒納豆の納豆菌数:約14億個
- 小粒納豆の納豆菌数:約21億個
- ひきわり納豆の納豆菌数:約24億個
納豆菌は納豆の表面で増えるため、大豆を割って皮を取り除くひきわり納豆は、その分表面積が広くなり、結果として最も多くの納豆菌を宿しているとのことです。納豆菌が多いということは、それだけ納豆の持つ健康効果も高まる可能性を示唆しています。この事実は、私にとって大きな発見でした。これまでは食感の好みで選んでいましたが、これからはひきわり納豆を選ぶ理由が増えました。
納豆を食べるタイミングは朝がおすすめ
血糖値対策として納豆を食べる場合、番組で強く推奨されていたのが「朝食での摂取」です。朝食に納豆を取り入れることで、血糖値が安定しやすくなるというのです。番組内では、朝食を食べない人の血糖値がどのように変化するか、そして朝食に納豆を取り入れた場合にどうなるかという検証も紹介されました。
例えば、朝食を摂らなかったカカロニ栗谷さんの場合、昼食後には血糖値が193、夕食後には247という高い数値を示していました。しかし、彼が朝食に納豆とおにぎりを食べた日には、昼食にプルコギ定食、夜にカレーライスを食べたにもかかわらず、夕食後の血糖値の上昇が以前よりも100も下がったという驚きの結果が示されました。これは、朝に納豆を摂取することで、その日一日の血糖値の変動に良い影響を与えることを明確に示しています。夏の暑い時期は血管が傷つきやすいため、血糖値の安定は特に重要になります。この情報を受けて、私も朝食に納豆を取り入れる習慣を始めようと思います。
セカンドミール効果とは
「林修の今知りたいでしょ!」で紹介された「セカンドミール効果」は、血糖値対策を考える上で非常に重要な概念です。これは、朝に血糖値を上げにくい食事を摂ることで、次に摂取する昼食後の血糖値上昇も抑えられるという、まさに驚きの効果を指します。番組の検証でも、朝食に納豆を摂ったことで、昼食後の血糖値上昇が抑えられたことが示されていました。
このセカンドミール効果の存在を知ると、「それならば、納豆を毎食食べればもっと良いのでは?」と考えてしまいますよね。しかし、番組では、納豆は発酵食品であるため、たくさん食べすぎると体調を崩す可能性もあることから、1日1〜2パックまでを目安にすることが推奨されていました。どんなに良い食材でも、適量を守ることが大切だということを改めて教えてくれました。このセカンドミール効果を意識すれば、無理なく血糖値管理に取り組めると感じています。
納豆の保存と加熱による効果
納豆の健康効果について考える際、保存方法や調理法による影響も気になるところです。番組では、この点についても興味深い検証結果が紹介されました。
- 冷蔵庫での保存と納豆菌の数
- 納豆菌は、冷蔵庫の中でも増え続けていることが示されました。買ってすぐの納豆の納豆菌数が約1360億個だったのに対し、冷蔵庫で1週間保存した納豆では約1800億個にまで増えていたのです。これは、冷蔵庫に保存していても納豆菌の活動が活発であり、さらに健康効果が高まる可能性があることを示唆しています。
- かき混ぜる回数とポリグルタミン酸
- 納豆をかき混ぜる回数が、ポリグルタミン酸の量に直接影響を与えるわけではないという意外な事実も紹介されました。しかし、かき混ぜることで得られる効果は別にあります。
かき混ぜることによって、ポリグルタミン酸が増加し、旨味成分であるグルタミン酸が生成されるため、より美味しく感じられます。納豆を混ぜてネバネバを増やすことで、ナットウキナーゼが胃酸で分解されるのを防ぐ効果も期待できます。
- 納豆をかき混ぜる回数が、ポリグルタミン酸の量に直接影響を与えるわけではないという意外な事実も紹介されました。しかし、かき混ぜることで得られる効果は別にあります。
- 加熱による影響
- 納豆のネバネバ成分であるポリグルタミン酸は熱に強く、60℃の熱々ご飯にかけても、また100℃の熱々料理に入れてもその効果は変わらないことが示されました。実際に、納豆チャーハンにすることで、納豆なしのチャーハンよりも血糖値の上昇が緩やかになるという検証結果も出ています。
- ただし、血栓予防効果で知られるナットウキナーゼについては、70℃以上で壊れてしまうため、血栓予防を目的とする場合は加熱しない食べ方が推奨されています。
これらの情報を知ることで、納豆を美味しく、そして効果的に食べるための選択肢が広がりますね。私もこれからは、料理に合わせて納豆の食べ方を変えてみようと思います。
血糖値急上昇を防ぐNG行動4選
番組では、納豆の「最強の食べ方」だけでなく、私たちが普段の生活で無意識に行っている、血糖値を急上昇させてしまうNG行動についても警鐘を鳴らしていました。これは納豆の摂取と合わせて、日々の食習慣全体を見直す上で非常に重要なポイントです。
- 食事を短時間で済ませる(早食い)
- 食事を急いで摂ると、胃の蠕動運動も早くなり、食べ物が胃から腸へ急激に移動します。これが糖の急吸収につながり、血糖値の急上昇を引き起こします。食事時間は20〜30分を目安にゆっくり食べることが推奨されていました。
- 食事と食事の間隔が長い
- 空腹時間が長く続きすぎると、次に食事を摂った際にインスリンの分泌が遅れることがあります。これが血糖値の急上昇につながる可能性があります。
- 夕食で炭水化物ばかり先に食べる
- 炭水化物を最初に大量に摂取すると、血糖値が急激に上がってしまいます。野菜やタンパク質から先に食べることで、糖の吸収を穏やかにできます。
- 食後すぐに大量に甘いものを飲む
- 甘い飲み物は、甘い食べ物よりも糖が吸収されやすく、血糖値を急激に上昇させます。飲む場合は食後ではなく、時間を空けて血糖値が下がってからにするのが良いでしょう。
これらのNG行動は、私たちが普段何気なく行いがちなことばかりです。私もついつい早食いをしてしまったり、食後に甘いものを摂ったりすることがあるので、これからは意識して改善していきたいと思います。血糖値の急上昇は、血管への負担だけでなく、頭痛やだるさの原因にもなるとのこと。健康的な生活を送るためにも、これらの点に注意を払うことが大切ですね。
どちらが血糖値が上がりやすい? 食材・食品クイズ解説
「林修の今知りたいでしょ!」の「納豆」特集では、日常生活で私たちが口にする様々な飲食物について、「どちらが血糖値が上がりやすいか?」という興味深いクイズ形式で解説していました。これらの情報は、日々の食選択に役立つ、目から鱗の知識ばかりでした。
1. 温かい麺 vs 冷たい麺
- ラーメン vs 冷やし中華
- 血糖値が上がりにくいのは:冷やし中華
- 理由: 炭水化物は冷やすことで「レジスタントスターチ」という難消化性の成分に変化します。これは消化されにくいため、糖の吸収が穏やかになり、結果として血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。ラーメンのような温かい麺類は、このレジスタントスターチが少ないため、血糖値が上がりやすい傾向があります。
2. お酒の種類
- ビール vs ハイボール
- 血糖値が上がりにくいのは:ハイボール
- 理由: ハイボールは蒸留酒に分類され、糖質がほとんど含まれていません。一方、ビールは醸造酒であり、糖質が多く含まれているため、血糖値が上がりやすいと言えます。お酒を選ぶ際も、糖質の有無を意識することが大切です。
3. コーヒーを飲むタイミング
- 食前のコーヒー vs 食後のコーヒー
- 血糖値が上がりにくいのは:食前のコーヒー
- 理由: コーヒーにはポリフェノールの一種である「クロロゲン酸」が含まれています。このクロロゲン酸は、食前に摂取することで血糖値の上昇を抑える効果が期待できるそうです。食後に飲むよりも、食事の前に一杯飲むことを習慣にすると良いでしょう。
4. 果物の選択
- スイカ vs バナナ
- 血糖値が上がりにくいのは:バナナ
- 理由: スイカは水分が非常に多く含まれており、まるでジュースを飲むように糖が体内に素早く吸収されやすい特性があります。そのため、血糖値が急上昇しやすい傾向にあります。対照的にバナナは、食物繊維なども含まれているため、比較的糖の吸収が緩やかです。
5. 冷たいデザート
- アイスクリーム vs かき氷
- 血糖値が上がりにくいのは:アイスクリーム
- 理由: アイスクリームには脂質が含まれています。脂質は消化を遅らせる働きがあるため、かき氷のように糖質のみが多く、かつ水分が多くて吸収が早いものに比べて、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。意外に思われるかもしれませんが、血糖値の観点からはアイスクリームの方が有利なのです。
6. パンの食べ方
- トースト vs バタートースト
- 血糖値が上がりにくいのは:バタートースト
- 理由: バターに含まれる脂質が、パンの糖質の吸収速度を緩やかにする効果があるためです。トースト単体で食べるよりも、バターを塗ることで血糖値の上昇を穏やかにできます。
7. サラダの具材
- ポテトサラダ vs チキンサラダ
- 血糖値が上がりにくいのは:チキンサラダ
- 理由: ポテトは炭水化物であり、糖質を多く含んでいます。一方、チキンはタンパク質が主成分です。タンパク質は糖質に比べて血糖値への影響が小さく、また消化に時間がかかるため、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。
8. パスタの種類
- ナポリタン vs カルボナーラ
- 血糖値が上がりにくいのは:カルボナーラ
- 理由: ナポリタンは糖質が中心となるソースですが、カルボナーラには脂質や卵のタンパク質が多く含まれています。これらの成分が糖質の吸収を穏やかにするため、ナポリタンに比べて血糖値が上がりにくいと言われています。
9. 味噌汁の種類
- 赤味噌汁 vs 白味噌汁
- 血糖値が上がりにくいのは:赤味噌汁
- 理由: 赤味噌に含まれる褐色成分「メラノイジン」に、血糖値の上昇を抑える効果があります。白味噌に比べて赤味噌にこの褐色成分「メラノイジン」が豊富であることが理由として挙げられます。
これらのクイズの結果は、私たちが普段の食生活で血糖値を意識する上で、非常に実用的なヒントを与えてくれます。日々のちょっとした選択が、体の健康に大きく影響することを改めて実感しました。
【林修の今知りたいでしょ!「納豆」血糖値急上昇を防ぐ最強の食べ方】の総括
・納豆は血糖値スパイク抑制に効果的で、心筋梗塞などの死亡リスク低減も期待される
・すぎおかクリニック院長の杉岡充爾先生が納豆の血糖値抑制効果を解説した
・血糖値スパイクは食後の血糖値の急激な上下動で、眠気やだるさを引き起こす
・納豆のネバネバ成分「ポリグルタミン酸」が糖質の吸収を穏やかにする
・納豆入りパスタは納豆なしに比べ、食後の血糖値上昇を大幅に抑制した
・朝食に納豆を摂ると昼食後の血糖値上昇も抑える「セカンドミール効果」がある
・納豆のちょい足し食材ベスト3はアカモク、キムチ、たまごである
・ひきわり納豆は表面積が広く、納豆菌が最も多く含まれている
・血糖値対策には納豆を朝食で摂るのが最もおすすめである
・納豆菌は冷蔵庫で増え続け、1週間で菌数が増加する
・納豆をかき混ぜる回数はポリグルタミン酸の量には直接影響しないが、美味しさやナットウキナーゼの保護に繋がる
・ポリグルタミン酸は熱に強く、加熱しても血糖値上昇抑制効果は変わらない
・ナットウキナーゼは70℃以上で壊れるため、血栓予防には加熱しない方が良い
・早食い、食事間隔が長い、炭水化物ばかり先に食べる、食後すぐに甘いものを飲むのはNG行動である
・カズレーザーと学ぶ。高血圧があの野菜で劇的改善!ナス活用術【2025年7月15日放送】
・ヒルナンデス「おくらと大葉のだし風」で夏を乗り切る!藤井恵さんの簡単絶品レシピの秘密
・ヒルナンデス「ナスの田舎煮」藤井恵さんの神レシピ!で食卓を豊かに【2025年7月15日放送】
・藤井恵さん直伝!ヒルナンデス発「枝豆きゅうりみょうがのしょうゆ漬け」で常備菜レパートリーを増やそう【2025年7月15日放送】
・ヒルナンデス!家事のプロが100均ダイソーで本当に役立つ激安家事ラクなグッズを紹介【2025年7月15日放送】
・あさイチ「冷製カルボナーラそうめん」夏を乗り切る究極の一皿!2025年7月15日放送
・あさイチ 「レモン香るひんやり春雨」夏バテ解消!絶品さっぱりレシピ2025年7月15日放送
・あさイチ「冷やしごま豆乳肉みそうどん」の魅力を徹底レビュー2025年7月15日放送
・ヒルナンデス!医者の自宅に潜入!新発見の食事術、7月14日放送回を徹底解説!日比野先生の食習慣とは?
・午後LIVEニュースーン「梅きゅうりのごま油オイスターあえ」を徹底解説!2025年7月9日放送